
「もうこんな仕事辞める!」と思う瞬間必ずありますよね?
最初はそれでも頑張ろうって思えていたはずです。
ですが、「辞めたい」と思う回数が増えれば増えるほど、
辞めることを真剣に考え始めているのではないでしょうか?
仕事を辞めることが決して悪いことではありません。
しかし、辞めたあとのことを考えずに辞めると、後悔することになりかねないです。
ここではみなさんが、後悔せずに辞められる方法をお伝えしていきます。

1. 仕事を辞めたいと思う人
働く人のほとんどが仕事を辞めたいと思っています。
では、仕事を辞めたいと思いながらも、今の会社で働き続ける理由は何なのか。
逆に、辞めたいと思っているのになぜ辞めないのか、なぜ続けているのか。
まずは辞められない理由を考えてみてください。
きっと、ほとんどの人は辞めるための行動を何もしていないからではないでしょうか?
では実際仕事を辞めた人はどのような理由で辞めているのか、
リクナビNEXTが行った退職理由の本音についての調査結果を基にみていきます。
出典元URL: https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/4982/
<退職理由のホンネランキング>
| 順位 | 理由 | 比率 |
| 1位 | 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった | 23% |
| 2位 | 労働時間・環境が不満だった | 14% |
| 3位 | 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった | 13% |
| 4位 | 給与が低かった | 12% |
| 5位 | 仕事内容が面白くなかった | 9% |
| 6位 | 社長がワンマンだった | 7% |
| 7位 | 社風が合わなかった | 6% |
| 7位 | 会社の経営方針・経営状況が変化した | 6% |
| 7位 | キャリアアップしたかった | 6% |
| 10位 | 昇進・評価が不満だった | 4% |
1位が「上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった」
2位に「労働時間・環境が不満だった」
3位は「同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった」
と上位3位をみてみると、
人間関係や会社の環境・待遇が原因で退職していることが多いことが分かります。
みなさんもこのランキングの中に当てはまるものがあったのではないでしょうか?
仕事をしていれば不満に思う事はもちろんあります。
我慢できること、我慢しきれないこと。
人によってどれだけのことに耐えられるのか差があるのも当然です。
スポーツをしている人によく「限界突破してやる!」と頑張っている人がいませんか?
その姿って見ていて心打たれますよね。
または実際自分がそういう人間だったという人もいるのではないでしょうか?
そのようなタイプの人によくあるのが、
仕事を辞めるということが、甘えや逃げだと思って我慢しすぎてしまうことです。
その挙句、うつ病になって仕事ができる状況じゃなくなってしまうということもあります。
仕事ができない状況になってしまうのが一番怖いことなのです。
仕事ができなくなるともちろん収入はなくなり、生活ができなくなります。
これからの自分の人生のためにも、辞めるべきかどうか考えるのは大切なことです。

2. 1度冷静に考える
まず1番に考えてほしいのは、
「辞めよう」と思っている気持ちは一時的なものではないかです。
仕事を辞めると決意している方、
仕事を辞めたあとのリスクについて考えたことがありますか?
もし、一時的な感情で辞めようとしているなら、一度冷静になって考え直すべきです。
・辞める理由は何なのか
・今の職場で改善できることはないのか
・なぜ今の会社に入ったのか
・辞める準備はできているのか
この4点についてよく考えてみてください。
もしかしたら、今辞めるべきではないと気付くかもしれません。
辞めてから、後悔なんてしたくないですよね。
そのためにも、今しっかりと考えることが大切なのです。
2つのリスクについて、
<収入が不安定>
まずは当然、収入面です。
転職先が決まっていれば別ですが、
そうでない場合この問題に頭を悩ますことになるでしょう。
簡単には見つからないかもしれません。
仕事を辞めて無職の状態が続くともちろん収入は0になります。
生活をしていくためには必ずお金が必要です。
その状態が続けば続くほど不安に陥り精神的にも疲れてくるでしょう。
<手続きが面倒>
ちなみに、仕事を辞めたあと必要な手続きがあることをご存知ですか?
「健康保険」「年金保険」「雇用保険」の3つの手続きです。
今までは会社が全て手続き等をしてくれていましたが、退職すると保険は喪失されます。
次の仕事が決まるまでの間、無保険というわけにはいきません。
また、保険に入っていない状態で病院に行けば、全額支払わなければいけないのです。
辞めたあとのことをよく考えた上で、辞める決意をするべきです。
2-1転職活動は2ヶ月かかる!?辞める前に転職活動はしておこう
転職先が決まっていない方。
「今すぐに辞めたい」という状況でなければ、
転職先が決まってから退職することをおすすめします。
転職サイト@typeが『初めての転職の平均活動期間』について調査した結果、
平均期間は約2.1か月です。
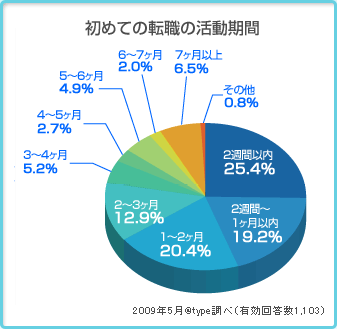
出典元 URL https://type.jp/s/first/f_period.html
グラフを見て頂けたら分かるように早く決まる人もいれば、なかなか決まらない人も当然います。
あなたがどれくらいの期間かかるのかは誰にも分かりません。
仕事を辞めてから転職活動を始めると、
なかなかいいところが見つからない、
内定がもらえないと焦ってしまい、結局後悔する羽目に…ということも考えられます。
また、転職活動期間が長くなればなるほど、転職はますます不利になっていきます。
無職期間が半年をこえると面接官のつっこみが厳しくなり、
せっかく面接まで進んでもそこでつまずいてしまっては意味がありません。
そういった点も踏まえると、在職中に転職先を見つけることが一番いいでしょう。
転職活動がリスクにならないように、余裕を持って転職活動を行ってください。

3. 転職をして良かったと思う人は8割!
リスクも全て踏まえた上で仕事を辞める決断をしたら、
あとは今よりも良い環境で働ける会社を見つけるまでです。
仕事を辞める理由がマイナスな理由であっても、
前向きな目標を持って転職活動を行ってください。
少しは気を紛らわすことができるかもしれません。
ちなみに、en転職が行った調査結果によると、
転職をして、「よかった」と思う人は全体の約8割を占めていることがわかります。
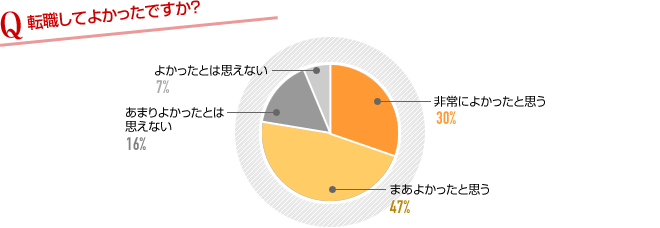
出典元 URL https://partners.en-japan.com/special/tenshokushinri/
転職活動は大変ですが、そこを乗り越えたからこそよかったと感じている人が多いのでしょう。
また、2つの意見として
<非常によかったと思う人の意見>
・居心地のよい会社に入れたから。
いろんな会社のスタイルを身をもって体験でき、より幅広い考え方をできるようになった。
いろんな会社で仕事をすることにより自信がついた。
・色々な経験が出来た事と、考え方が多様化し、仕事に対する目的意識が向上し、何より自己の成長が感じられた。
・転職により、自分が最も望む仕事内容に近い職種を得る事ができ、自分の能力・視野が劇的に広がった為。元の会社で頑張り、希望の職種を目指すのも一つの可能性だったが、大きな組織の中でそれがいつ叶うのかを待つより、思い切って新しい環境を選択した。
<よかったとは思えない人の意見>
・仕事内容などよく分からずに転職してしまった。
・早く勤めたいという気持ちの焦りから次の会社の業務など、あまり考えずに仕事に就いた事。
・家族があるので離職後の再就職(収入が途絶えては生活できない)を急ぐあまり再就職先の条件を甘くし、妥協して就職して後悔している。
『よかったと思えない』の2割に入ることだけは避けたいですよね。
辞めたことを後悔しないためには、今よりもいい転職先を見つけるしかありません。
そのためには、会社の見極めが肝心です。
「なかなか決まらず、焦って次の仕事先を決めてしまった」
なんてことがないように、少しでも早い転職活動を始めてください。
どのような会社に入りたいか条件を考えてみましょう。
また、これだけは妥協できないという点を絞っておいた方が仕事も探しやすくなります。
この機に、人生設計や未来計画を立ててみるのもいいかもしれません。
転職活動はやり方によって結果が出るまでに大きな差が生じます。
転職先の探し方や効率の良い転職活動については
下記の記事で詳しく解説していますので是非、参考にしてください。
https://labo.i-youth.co.jp/job/160.html
転職先で同じ思いをしないためにも、
記事の中でお伝えしている「口コミサイト」は是非利用してみてください。

4. 退職理由には建前が必要!
目次1では、退職した人の本音の理由をご紹介しました。
例え辞めたい理由が「上司のやり方が気に食わない」だとしても、
その理由をそのまま伝えることはよっぽどの根性がない限りできませんよね。
社会人としても取るべき行動ではありません。
『嘘も方便』ということわざを聞いたことはありますか?
嘘をつくことは悪いことですが、時と場合によっては必要なこともあるということです。
そこで必要になってくるのが、『本音と建前』の使い分けです。
辞める理由に対して、
上司や会社側にしっかりと理解・納得をしてもらう建前の理由を考えなければいけません。
まずは、建前の理由をご紹介します。
<建前の理由例>
・今の職場に不満はないが、○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい
・元々、自分の夢であった○○の分野に挑戦したい
・自分のステップアップのために、今までの経験を活かして新しい環境で自分の力を試したい。
・新たにやりたいことを見つけたので、資格をとるため勉強に専念したい
辞めたい理由がマイナスなことであれば、建前の理由を考える必要があります。
ですが、引き留めてくる会社や上司ももちろんいます。
他の部署への異動をもちかけられることもあるでしょう。
そこで、引き留められないようにするためのポイントとして、
・退職時期は、会社の繁忙期とずらす
・上司への相談のタイミングは1ヶ月以上の余裕を持つ
・「退職するべきか」の相談はしないこと
・絶対に退職したいなら、「条件」を退職理由にしない
・「かならず退職する」という強い意思を持つこと
という点に気をつけて頂けたら、引き留められる可能性は低くなるでしょう。
それでも強引に引き留められるという可能性も考えられます。
そのときは、
「転職先が決まっている」や、「退職の意思が揺るがない」ことを伝えるようにしましょう。
どのような理由であなたを引き留めているにしても、
必要としてくれていることに違いはありません。
上司の角を立たせないためにも、
「身に余るお言葉ありがとうございます。ですが、辞める意思に変わりはありません。」
など一言添えることで印象も変わってくるでしょう。
感謝の気持ちと、この会社ではできないことがあるという旨を伝えるようにしてください。
また、個人的な事情での辞め方は、
・結婚することを機に、寿退社
・旦那の転勤で、地方に引っ越すことになった
・親の介護に専念しないといけない状況になった
・家業を継ぐことを決意した
・健康状態が悪化してしまい、静養することにした
などがいいでしょう。
しかし、結婚する予定のない人や、
介護をする状況ではない人など全く関連性のない理由や嘘はよくありません。
いい辞め方ができたとしても、あとで嘘がばれるとあなたの信用を失うことになります。
これからも関係を続けていきたい人もいるはずです。
また、どこかで繋がりができるという可能性も考えられます。
このような理由にするときは本当にその予定がある場合だけにすることをおすすめします。
4-1. 円満退職までの6つの順序
円満退職するためには退職理由だけを工夫すればいいのではありません。
退職理由や退職の意思をまず誰に伝えるべきなのか、
伝えたあと退職までどうやって進めていけばいいのかという退職までの順序をお伝えします。
<円満退職するための6つの順序>
①就業規則の確認
辞めると決意したら、まずは会社の就業規則の確認をしてください。
会社の就業規則に、「退職の意思表示は○か月前までに」と記載されていることが多いです。
民法では「14日前まで」に退職の意思表示をすればいいことになっていますが、
円満退職するためには就業規則に従うことが一番でしょう。
②直属の上司に相談
まず、最初に伝えるのは直属の上司です。
直属の上司を飛び越えて、上役や別部署の上司に伝えることはいけません。
同僚や部下などに話すのもやめておきましょう。
伝える際には、一方的に退職の意思や退職希望日を伝えるのではなく、
あくまで相談ベースということを忘れてはいけません。
しかし、ここでの相談は退職するかしないかではなく、
退職したいのでふさわしい時期や引き継ぎについての相談をしましょう。
また軽い気持ちではなく考え抜いた末の結論であること、
退職後もつながりを大事にしたいということを伝えることも大切です。
③退職願・退職届提出
退職交渉を終えてから、退職願・退職届を提出します。
退職の切り出し時に退職届等を提出すると受取手が困惑してしまいます。
退職交渉が終わってから提出するようにしましょう。
また、退職願・退職届のどちらを提出するべきかは、
上司に相談するか就業規則を見て確認しましょう。
就業規則に記載されていないなど、分からない場合は退職願を提出します。
退職願は退職届と比較して柔らかい印象を与えるためです。
④引き継ぎ
退職日が決まったら、そこから逆算し引き継ぎのスケジュールを立てることは必須です。
最後まで責任を持って業務の引き継ぎや、残務処理を行ってください。
後任者にメモを取ってもらったり、口頭で伝えたりするだけではいけません。
業務の進歩状況や内容、
踏まえるべき留意点などをいつでも参照できるように、資料を作成しておくといいでしょう。
資料を見れば何でも分かるというのがベストです。
⑤社内外への挨拶
取引先への挨拶や社内外の関係者にできるだけ対面で挨拶をしに行くことも大切です。
そのときに、後任者と一緒に行こといいでしょう。
後任者の紹介を行っておくことで、
取引先と後任者がスムーズに新たな付き合いを始めることができます。
⑥社内への挨拶まわり
最終出社日にはお世話になった人への挨拶まわりはお忘れなく。
それほど関わっていない人も、一言「お世話になりました」と伝えましょう。
良い印象を与えることができます。
<退職を切り出すタイミング>
退職は自分の人生だけでなく、所属する会社や組織に少なからず影響を及ぼすもの。
①でも記載したように、民法では「14日前まで」に退職の意思表示をすればいいことになっています。
(正確には14日経過後の15日目に退職できる)
会社の就業規則に、「1か月前までに退職願または退職届を出さない場合、退職を認めない」
と記載されていても法律が優先されるため、従う必要はありません。
しかし、円満に退職するためにも、
退職の意志が固まり次第、なるべく早く退職の意向を直属の上司に伝えましょう。
2~3か月前がベストです!
また、プロジェクト終了時期や仕事のキリに合わすなど、繁忙期は避けるようにしましょう。
会社や同僚に配慮することも大切です。
今の仕事をやりきった上で、同僚に迷惑を掛けず、
キリの良いタイミングで退職するのがベストです。
プロジェクト単位の働き方ならば、その切れ目。
管理部門などは、年度末や決算期、四半期などの期末が良いでしょう。
5. まとめ
1番初めにも言いましたが、仕事を辞めることは決して悪いことではありません。
ですが、1人で悩んで決断しないようにしてください。
信頼できる友人や、家族に相談することで客観的な意見を聞くことができます。
そして、最後に決断するのは自分です。
考え抜いた末の結果なら、どちらにしても前向きに考えていきましょう!




