
「業界研究ってどんなやり方で取り組めばいいの?」
といったように、
業界研究のやり方に模索している就活生の方は多いのではないでしょうか。
忙しい就活生の身。デキるだけ効率良く終わらせたいですよね。
かと言って、早く適当に終わらせるのは絶対NG!
業界研究は就活において「ひじょーーーーに」大切な準備作業だからです。
というワケで今回の記事では、
効率良くそしてパーフェクトな「業界研究のやり方」について解説していきます。

1.業界研究で成果を出すために・・・
価値ある業界研究にするためには、事前準備が不可欠。
いきなり業界研究に取り掛かるのは絶対NGですよー。
何事にも順序が存在します。
業界研究をする前に必ず自己分析をしておきましょう!
「自己分析は完璧!」
という方は読み飛ばしてOK!
就活の準備作業を順番にお伝えすると・・・
1.自己分析
2.業界研究
3.企業研究
↑こんな感じ。
就活における「3大必須準備作業」ですね。
なぜ、この順番で進めていくのかと言うと・・・
ステップ1
「自己分析」で、
自分の長所や短所などを把握し、
それを基に、
「どんな仕事であれば自分はやりがいを持てるのか」
「仕事に対する適正」
「自分は将来仕事で何を実現したいのか」
について把握し、
ステップ2
「業界研究」で、
自己分析で把握した自分の情報を元に
どの業界であればそれが実現できるのか調べる。
ステップ3
最後に「企業研究」で、
企業ごとの特徴について見ていきながら、
実際に志望する企業を選んでいく。
↑こんな感じだからです。
そのため、まずは自己分析に取り組んでください!
自己分析については、
以下の記事で説明していますので、
自己分析がまだの方は先にこちらをチェック!
<なぜ、就活生は自己分析をしなければならないのか>

2.始める前に知っておきたい業界研究チェックポイント!
自己分析をしっかり行えた方は、
早速!業界研究に取り掛かりましょう!!
早めにスタートさせておいて損はありません!
むしろ、メリットしかありません!
ここでは、具体的な「業界研究のやり方」についてお伝えする前に、
業界研究を行う時に意識しておく点を先にお伝えしていきます。
道標的な感じですね。
チェックしておくべきポイントは、
・業界の市場規模(業界全体で売り上げがどれくらいか)
・業界のビジネスモデル(誰に対しての商売なのか、儲けの仕組みなど)
・業界の現状と課題そして展望について考える
最低限この3つ!
なぜ、この3点をチェックするのか簡単に解説していきます。
<業界の市場規模>
必ず最初に確認すべきポイントそれが業界の市場規模。
全体像が把握できていない状態で進めてしまうと時間のムダに・・・
市場規模は業界によって非常に差があるため、
その違いが分かるだけでも結構面白いです。
必ず最初に確認するようにしましょう。
<業界のビジネスモデル>
続いてチェックするのは、業界のビジネスモデル。
・どうやって事業を成り立たせているか
・誰を相手にしている商売なのか(BtoB? BtoC?)
この2点が把握できてくると、
自分がこの業界に就職した時にどんな仕事をするのかが見えてきます。
業界の主要企業について、見ていけば把握しやすいかと。
業界が独立して事業を行うケースは珍しいので、
この段階で関連業界についても目を向けるようにしましょう。
<業界の現状と課題そして展望>
ここを把握するのが業界研究の1番のポイント。
現状について調べ、課題を調査、そして展望を考察する。
まさに業界研究といった感じですね!
・何が原因で業界の調子がいいのか
・逆に何が原因で業界の将来性が危ういのか
ただ単に調子の良い悪いではなく、
しっかりとその原因まで詳しく調べていきましょう。
自分の将来を預ける業界のことは、徹底的に調べておいて損はありません。

3.業界研究のやり方を徹底解説!!
前置きが長くなりましたが、
ようやく!具体的な業界研究のやり方についてお伝えしていきます。
方法としては、
1.おなじみ「業界地図」
2.「〇〇業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」を活用する
3.就職情報サイトから情報を集める
4.業界研究セミナーに参加する
↑この4つ!
以下で順番に解説していきます。
3-1.おなじみ「業界地図」はマストバイ!
何から手をつければ・・・
となりがちな「業界研究」
先ほどチェックポイントでもお伝えしたように・・・
まずは、全体像を掴むため、
「会社四季報 業界地図」を活用しましょう。
<会社四季報 業界地図>
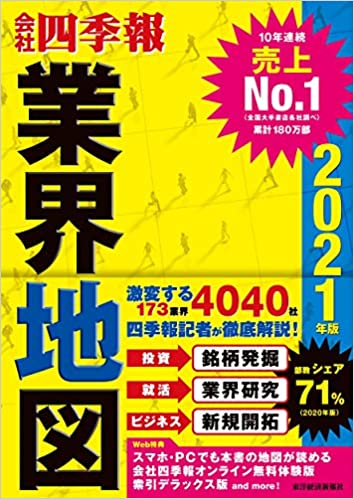
出版社:東洋経済新報社
URL: Amazon
業界地図の素晴らしい点は、
何と言ってもその見やすさと分かりやすさ。
難しく感じがちな業界研究のハードルをグッと下げてくれること間違いなしです。
恐らく、この業界地図でカバーできていない業界はありません。
あまり知られていない新しい業界についても解説してくれているので、
「志望している業界が特に決まっていない・・・」
という方はまじでマストバイ!
業界内の相関関係や業界内での順位もかなり参考になるはず。
・業界の現状や将来性
・調子を落としている原因
この2点を分かりやすく解説してくれているのも非常に親切。
なんとそれだけでなく、
業界研究を進めていく上で、必須の経済用語を分かりやすく解説してくれています。
サクッとストレスなく業界の基礎知識を習得するために、
必ず購入しておきましょう!
3-2. 掘り下げるために「〇〇業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」を活用する
様々な業界を知ることが出来るので、
先ほどご紹介した「業界四季報 業界地図」がまずは1番オススメ。
既に特定の業界が決まっている、
もしくは業界地図で業界研究を進めていくうちに掘り下げたい業界が見つかった方。
以下のシリーズが非常にオススメ。
それは、
「〇〇業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」シリーズです!

↑こんな感じの表紙。
参考URL:Amazon
食品、
アパレル、
建設、
ホテル、
医薬品、
通信、
不動産、
物流、
保険、
旅行、
化粧品、
金融、
広告、
銀行、etc・・・
恐らくほぼ全ての業界を網羅してくれています。
業界の仕組みから儲けのシステム、業界が抱えている課題や将来性など。
非常に分かりやすくまとめてくれています。
ビジネスモデルの把握はこの1冊で恐らく完璧。
読めば分かりますが、
業界地図とこの本の組み合わせはかなり強力です!
掘り下げて調べたい時に重宝すること間違いなし!
3-3.PC派のあなたは就職情報サイトを活用!
今やサイトで有益な情報を無料で収集できる時代。
本当に便利な時代になりましたね・・・
これは、活用しない手はない!
というワケでご紹介するのは、ご存知マイナビさん。

「無料で利用できるのに、こんなにクオリティ高いの?」
って驚くこと間違いなしです。
業界の概要から業界の現状や課題と展望などなど。
業界の動向を非常に分かりやすく解説してくれています。
それだけでなく、
・業界に関する豆知識
・知っておくべき業界関連用語
・その業界ではどんな仕事に就くのか
までしっかりとまとめてくれています。
また、同じページで職種研究のページもあります。
・どんな仕事なのか?
・どんな能力やスキルが求められるのか?
知っておきたい情報が盛りだくさん。
是非、併せて活用しましょう!
そして、続いてもマイナビさん。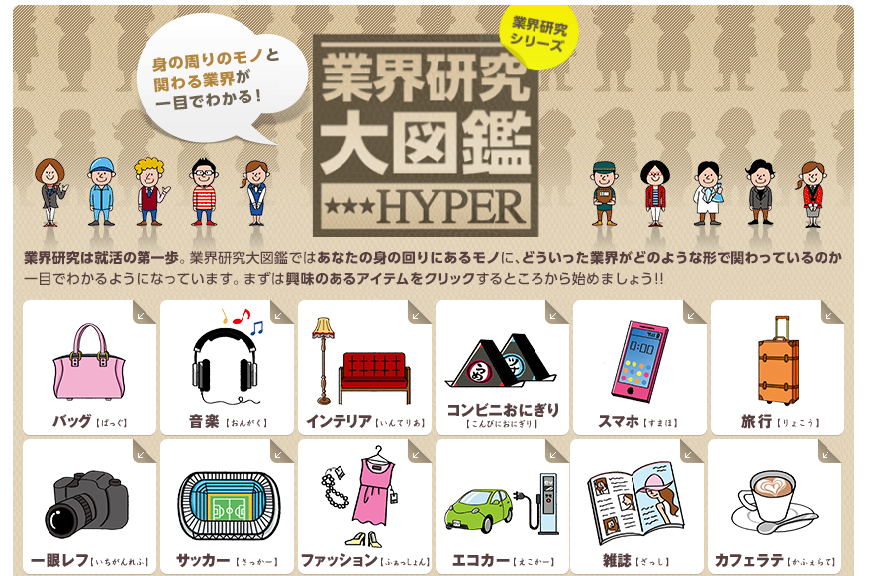
リンク先:マイナビ2021業界研究大図鑑HYPER
このページは、先ほどご紹介したものに比べて情報量は落ちますが、
独自の視点から業界について解説してくれています。
そこが結構面白い。
例えば、バックをクリックすると、
バックがあなたに届くまでに「どんな経緯を歩んでいくのか」
可愛らしいイラストでシンプルに解説してくれています。
これを見ると、
各業界が密接に関わりながら事業を行っていることが一目瞭然。
関連業界の把握に役立ちますので、
先ほどのサイトと併せて是非とも活用してください。
3-4.業界研究セミナーも活用しよう!
最後にご紹介する「業界研究のやり方」は業界研究セミナー。
開催場所や、スケジュールの関係がありますので、
全ての方が取り組めるやり方ではありませんが、
参加できる方は積極的に参加しましょう。
なんといっても、
その業界のプロから直接ハナシを聞けるのは非常にタメになります。
気になる内容を直接質問できるのは、ありがたいですね。
気軽に参加できるセミナーが多いようですので、
「具体的な方向性がまだ決まっていない・・・」
という方には特にオススメです。
業界研究セミナーに参加することで、
志望業界の方向性を定めることが出来るでしょう。

4.業界研究はノートにまとめて保管する
業界研究はやって終わりではもったいないです。
せっかく情報を集めて分析した成果はノートに保管しておきましょう。
いつでも見返せますし、新しい情報をその都度書き足すことができるので非常に便利。
フォーマットは以下のような感じで作っていただければいいかと思います。
<業界研究ノート:フォーマット>
| 業界研究 | |
| 業界名 | |
| 市場規模 | |
| 仕事内容 | |
| 業界の現状 | |
| 業界の課題 | |
| 業界の展望 | |
| 業界の主要企業 | |
| 関連業界 | |
| 業界の平均年収 | |
| 業界の平均年齢 | |
業界研究は一度取り組んで終わりではありません。
気になった情報はその都度ノートに書き足していきましょう。
説明会やOB・OG訪問など、様々な機会で情報は追加されるはずです。
他の就活生に差をつけるために、
常にアンテナは張り続けておきましょう。
5.まとめ
しつこいようですが、いきなり業界研究に取り組むのはNG。
まずは、自己分析にしっかり時間をかけてください。
業界研究は一度取り組んで終わりではありません。
アンテナを常に張り続け新聞など最新の情報も積極的に集めていきましょう!




