
「グループディスカッションではどんなテーマが出てくるのか」
気になっている就活生の方は多いのではないでしょうか?
気になる気持ちは分かりますが合格することを考えると、
正直テーマ自体はあまり気にしなくても大丈夫です。
グループディスカッションには大きく分けると4つのパターンがあり、
パターン毎の対策がしっかり取れていればさほど難しいものではありません。
参考までにどんなテーマがあるのかご紹介していきながら、
パターン別の対策とGDを突破するための練習方法について解説していきます。

1.グループディスカッションはテーマよりもパターンを知ることが大切
冒頭でもお伝えしたように、
グループディスカッションのテーマはあまり気にしなくて大丈夫です。
あらかじめ「こんなテーマで行いますよー。」
と教えてくれる場合は別ですが・・・
GDのテーマはあなたが受ける企業の数だけ存在します。
しかし、GDのパターンはたったの4つしかありません。
しかも実はパターンによって企業が求めている内容が異なるのです。
選考を突破することを考えると、
各パターンの対策を知っている方が何倍も効果的ですよね。
GDの練習をする場合も同じです。
様々なテーマで練習するよりも、
各パターンをまんべんなく練習した方がはるかに効果的かつ効率的。
グループディスカッションを突破するためには、
各パターンの対策を知っておく。
対策を知った上で各パターンの練習をする。
この2点がカギとなってきます。
というワケで以下では、
・グループディスカッションの各パターンの対策
・パターンごとのテーマ例
・グループディスカッションの練習方法
について解説していきます。
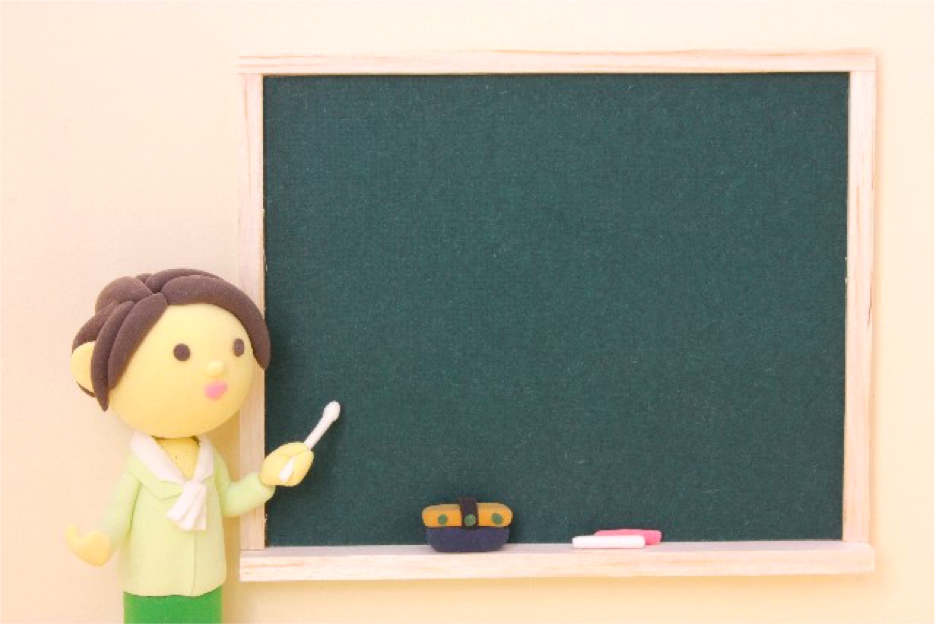
2.グループディスカッション4つのパターンとパターン別の対策
グループディスカッションのパターンとは、
1.自由式グループディスカッション
2.二択式グループディスカッション
3.選択式グループディスカッション
4.解決式グループディスカッション
↑この4パターン!
これ以外のパターンはGDに存在しません。
(恐らく・・・汗)
名前だけでは、イメージしづらいかと思いますので、
パターン毎にテーマの例を見ていただきながら、
それぞれの対策を解説していきます。
2-1.自由式グループディスカッションの対策とテーマ例
<自由式グループディスカッションのテーマ例>
・10年後携帯電話はどうなっていると思いますか?
・仕事ができる人の条件を5つあげてください
・当社の新しいキャッチフレーズを考えてください
・「生きる」とはどういうことですか?
・モテる男性とモテる女性の定義を決めてください。
<自由式グループディスカッションの対策>
このパターンが1番簡単です。
テーマ例を見ていただければ分かるように、
自由式には基本的に答えがありません。
つまり、答えのクオリティは求められません。
プロセスが重視されるタイプです。
<対策のポイント2つ>
・正解がないので、自分の意見をしっかり伝える。
ただ単に伝えるのではなく根拠を基に伝えるようにしましょう。
Ex「生きる」とはどういうことですか?の場合。
生きるとは食べることです。
なぜなら、人間は食べないと死ぬからです。
↑答えの内容は気にしないでください(笑)
結論から伝え、「なぜなら~」みたいな感じで伝えるのがポイントです。
・相手の意見をしっかり聞く。
GD全般に言えることですが、
相手の意見をしっかり聞き相手の意見を尊重することが大切です。
間違っても「その意見はどうかと思う」
など頭ごなしに否定するのはやめましょう。
この2つのポイントを意識しておくようにしましょう。
2-2.二択式グループディスカッションの対策とテーマ例
<二択式グループディスカッションのテーマ例>
・死刑制度はありか?なしか?
・消費税増税の是非について
・子供に小学生の時からスマホを持たせるのはありか?なしか?
・成人年齢18歳に賛成か?反対か?
・道州制に賛成か?反対か?
<二択式グループディスカッションの対策>
このパターンは世間でも意見が分かれるような内容が多いです。
対策を立てる前に、
新聞などに目を通す習慣をつけ時事ネタにある程度詳しくなっておく必要があります。
意見が分かれる内容が多いため、選択する答えよりも「なぜそれを選択したのか」
根拠がより重視されるパターンです。
<対策のポイント2つ>
・論理的に意見を伝える
論理的に意見を伝えられるかどうかがカギです。
論理的に伝えるために発言は「CRF」でまとめる意識を持ちましょう。
Conclusion(結論)→Reason(理由)→Fact(具体例)
Ex.死刑制度はありか?なしか?の場合。
死刑制度はありに賛成です。
なぜなら、死刑制度を廃止すると犯罪が増えるからです。
実際に他国では死刑制度を廃止したことにより、犯罪が増加しているからです。
↑答えのクオリティは気にしないでください。(;´・ω・)
イメージを掴んでいただければOKです!
・メリットとデメリット両方を考える
メリットの面だけにこだわるのではなく、
デメリットまでしっかり考えられているかが非常に大切になってきます。
始まった時に、
「みんなでそれぞれのメリットとデメリットを挙げていきませんか?」
と提案してみるのもいいかもしれません。
物事には必ずメリットデメリットがあります。
そこを深く掘り下げられるかが大きなポイント。
Ex.死刑制度はありか?なしか?の場合。
犯罪抑止力というメリットがある一方、
死刑制度があることによって死刑になりたくて、
非常に重い犯罪を犯す人がいる。
↑みたいな感じです。
2-3.選択式グループディスカッションの対策とテーマ例
<選択式グループディスカッションのテーマ例>
・子供に1つ習い事をさせるとしたら何を選びますか?
「柔道・剣道・空手」
・オリンピックの新競技はどれにするべきですか?
「野球・空手・スケートボード・スポーツクライミング・サーフィン」
・当社がM&Aを行うべき会社を選んでください
「A社・B社・C社」※それぞれの会社の資料を基に
<選択式グループディスカッションの対策>
選択式は自由式と似ており、
GDにおいては、そこまで難しいものではありません。
自由式と二択式が合体したもの。
みたいな感じで思っていただければ大丈夫です。
各メリット、デメリットはしっかりと掘り出しましょう。
どのメリットを重視して、どのデメリットを軽視するか。
論理的に議論するようにしましょう。
テーマに関しては、
M&Aのように資料を基に進める場合もあるので難しいことも多いです・・・
<対策のポイント1つ>
ポイントは数ある選択肢の中で、
いかに合理的な答えをチームとして出せるか。
この1点です!
そのためには、参加者1人1人の意見(選択肢)を出すのではなく、
先にテーマのゴールについて議論していく方法がベストです。
Ex. オリンピックの新競技はどれにするべきですか?の場合。
例えば、オリンピックで新競技を追加する目的は何か?
オリンピックに関心を集めるのが目的であれば、
シンプルに競技人口が多い競技を選ぶのがベストでしょう。
↑こんな単純なワケないですけど・・・
選択する上での選択基準について議論できていれば、
より活発な議論になり合格しやすくなるでしょう。
2-4.解決式グループディスカッションの対策とテーマ例
<解決式グループディスカッションのテーマ例>
・日本の少子化を改善するには?
・売上が下がっているファミレスを改善するには?
・交通事故を削減するには?
・当社の課題を挙げ、解決策を考えてください
・地球温暖化を解決するには?
<解決式グループディスカッションの対策>
この解決式が1番難しいです・・・
現実世界で直面している課題や、
会社が抱えている課題など、、、
大きな問題に対して解決策を提示しなければならないからです。
1回トライすれば分かりますが本当に難しいです。
ある程度現実的な解答を提示しなければならないのが厄介な点。
しかも内容が高度なため、
効率良く議論を進めていかなければ制限時間内に終わらないという危険性があります。
<対策のポイント1つ>
・順序立てて議論を進めていく
どれだけ難しいテーマでも以下の順序を守りましょう。
1.どんな解決策があるか議論する
2.その解決策を実行する際の問題点について議論する
3.以上に基づいてどの解決策が現実的か議論する
Ex. 交通事故を削減するには?の場合。
解決策:全ての車に事故防止装置を取り付ける
問題点:それを取り付ける費用はどうするのか?
結 論:費用が掛かりすぎるため、現実的ではない↑イメージを掴んでいただければOKです・・・
解決式は今までお伝えした対策を全て含めたものだと思っていただければ・・・

3.グループディスカッション1番の対策は結局練習すること
本気でGDを通りたい場合は、
各パターンの対策を参考にしてたくさん練習しましょう。
苦手意識を持っている方は尚更のこと。
セミナーに参加したり、
グループディスカッションの対策本をいくら読んだりしても、
すぐに上手くなるワケではありません。
「こうすれば評価される」と頭で理解できていても、
実際にその動き方をしなければ自分の力にならないのです。
スポーツに例えると分かりやすいかと。
「こうすれば上手くなる」的な本をいくら読んでも上達しないですよね。
コーチの的確なアドバイスをいくら聞いてもそのままにしていれば、
アドバイスを聞いていない状態とほとんど変わらないですよね。
その情報やアドバイスを基に練習し、試行錯誤して初めて上達するものです。
本気で合格したければ、10回くらい練習してください。
3-1.グループディスカッションの効果的な練習方法
1:仲間を集める
まずは、メンバーを集めましょう。
人数は4人~8人。同じ就活生じゃなくても大丈夫です。
真剣に取り組んでくれる方をチョイス!
2:テーマと時間を決める
GDのテーマと時間を決めます。
テーマはどんなテーマでも構いません。
最低でも各パターンんのテーマは1回づつ。
今は便利な時代になったもので、GDのテーマなんてネットで探せばいくらでも出てきます。
先ほどお伝えしたテーマを参考にしてもOKです。
例えばこれを1つの参考にしてみてください。
参考元URL:(公式)15.16卒GDお題実例集Twitter
時間はテーマによって自由に決めましょう。
本番は30分~長くても50分の時間がほとんどです。
そのため、練習もその範囲内の時間で設定しましょう。
3:役割を決める
代表的な役割は、
・司会
・書記
・タイムキーパー
↑この3つ。
1つの役割だけ練習するのではなく、必ず全ての役割を練習しておいてください。
本番のGDでは、自分が得意な役割を選べるとは限りません。
どの役割になってもいいようにバランスよく取り組んでください!
+α必ず試験官役を置いておきましょう。
試験官を置く理由は後でフィードバックを行うためです。
4:撮影する
少し恥ずかしいかもしれませんが、せっかくの練習を無駄にしないために、
練習中はスマートフォンなどで撮影してください。
後で見直すと非常に勉強になります。
客観的に見ることが出来るので、
「自分の課題」について明確に把握できるからです。
全体が撮影できるように少し工夫して、
映ることを確認してからGDを開始するようにしましょう。
5:練習が終わったら必ずフィードバックを行う!
練習してそのままにしておくのは、
非常にもったいない!
終わったら必ずフィードバックを行うようにしましょう!
フィードバックの内容は、
・テーマに沿った発表ができていたかどうか
・各自が役割を全うできていたかどうか
・チーム全員が議論に参加できていたかどうか
・各自の良かった点と改善点
この4点です。
試験官役の人は適格なフィードバックが行えるように、
議論をじっくりと見ておきましょう。
グループディスカッションの合格率を上げるためには、とにかく練習する。
結局、何事も練習しなければ上達しないのです。
4.まとめ
グループディスカッションのテーマを気にするよりも、
各パターンを知りパターンごとの対策を把握しておきましょう。
そしてそれを基に練習する!!
これがグループディスカッションの合格率を上げる1番良い方法です。




