
現在の会社を辞めることは決意したが、
一体どのような方法を取ればいいのかわからないという方、多いのではないでしょうか?
会社を辞めたいと思っているが、なかなか言い出せずにいる方もいるでしょう。
この記事では、会社を辞めたいと思ったらすべき事を解説していきます。

1.会社を辞めたいと思ったら
<一度冷静に考えてみる>
会社を辞めたいと思っている人のほとんどが、現在の会社になにかしらの不満を感じている人です。
「その不満を抱えてでも、今の会社に残るメリットがあるのか」をまず考えてみてください。
メリットがないようであれば、会社を辞めて今すぐ転職活動することをオススメします。
メリットがあるのであれば、現在の会社に残るリスクや不満と天秤にかけてみてください。
メリットが勝つようであればそのまま続けた方が良いでしょう。
しかし、不満やリスクの方が勝つようであれば、転職へと一歩踏み出す勇気を出しましょう。
就業中でも転職活動は行えます。
転職活動を行い、いろいろな会社を見てみると良いでしょう。
現在の会社より良い会社がたくさん出てきます。
仕事へのやりがいを求めるのか、年収にこだわるのか人それぞれあるでしょう。
少なくとも、不満を感じている現在の会社よりも魅力的な会社に出会うことが出来るはずです。
なにも現在の会社にしがみつく事はないのです。
<いつ、辞めることを伝えるか?>
民法上では退職の意思表示から2週間を過ぎれば、
いつでも辞められるようになっています。
しかし、会社には就業規則が存在し、
「1ヶ月前に申し出る事」などの規定が設けられている事がほとんどです。
円満退社を目指すなら、就業規則の方を尊重すべきです。
またボーナスを貰ってから退職したいという場合にも注意が必要です。
ボーナスとは本来、過去の業績に対する報酬と今後の働きへの期待が含まれています。
賞与額が決まる前に退職を申し出ると査定が下がり、ボーナスが減額される可能性があります。
ただし、半分以下になるなど、
あまりに大きな減額は、不当として労働基準監督署などに相談しましょう。
いつまでにという決まりは無いが、
退職を決意したらなるべく早く、遅くても1ヶ月前までに報告することが、円満退社のポイントです。
<必ず直属の上司へ伝える>
退職届を出す前に直属の上司に相談という形で話を切り出しましょう。
というよりも基本的には直属の上司に退職の意を伝えるのが一般的です。
ここを飛ばして社長や部長に先に話をしてしまうとトラブルの原因になりかねます。
直属の上司から退職の了承を得る事ができたら、そこから直属の上司が部長や社長と
「後任人事や退職時期に問題は無いか」など話し合い方針を決定します。
同僚や先輩部下に話すのもここまでやめておいた方が無難です。
正式に通達されるまでは周りに話すのは極力やめておきましょう。
<退職理由を伝える>
退職する際、必ず退職理由を聞かれます。
本音で言えば現在の職場環境に不平不満が退職理由の人がほとんどでしょう。
しかし、不平不満を全て話してしまったら、円満退社というわけにはいかないでしょう。
ポイントとしては、「個人的な理由」を退職理由として話しましょう。
例えば、「キャリアアップをする為に新たな環境でチャレンジしたい」や
「○○に興味があり、それに関わる仕事がしたい」など、
夢の実現など前向きな退職理由の方が納得して送り出してくれます。
<退職願を作成する>
直属の上司に退職の意志を伝え、承諾を得られた場合は「退職願」を作成します。
出すタイミングについては、会社から求められてからでOKです。
基本的には直属の上司に手渡しで渡すのがベストです。
会社によっては人事部に直送という場合もあります。
会社に規定のフォーマットがある場合はそれに従って記入しましょう。
特に決まった規定がない場合は、手書き、パソコンでの作成どちらでも構いません。
以下で退職願の書き方について解説していきます。
・最初に「退職願」と書きます。「辞表」や「退職届」などは避けましょう。
・書き出しは「私事」です。退職願と書いた次の行の下の方に書きましょう。
・退職届に記載する退職理由は「一身上の都合により」とし、具体的な理由は書きません。
・退職予定日を記入しましょう。
・退職届に記入する部署名などは正式名称で書きましょう。
・自分の名前の後に印鑑を忘れずに押しましょう。
・宛名は社長宛にします。
それでは簡単にですが、実際に例を作ったので参考にしてみてください。
| 退職願 私事、一身上の都合により、平成○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 平成○年○月○日○○部 ○○課自分の名前 印○○○○株式会社代表取締役社長 ○○○殿 |

2.退職願を出してからの動き
ここでは、退職願を提出してからの動きについてお伝えしていきます。
<引継ぎに手を抜かない>
会社を辞めるからと言って、
引継ぎをおざなりにすると残された社員に大きな負担を背負わせてしまうことになります。
退職の理由がどんな理由でも引継ぎだけはしっかりと行うようにしましょう。
退職日が決まったなら、そこから逆算し引継ぎのスケジュールを立てましょう。
業務を引き継いでもらう相手に口頭で伝えるのではなく、
あらかじめ自分で資料を作成しておくのがベストです。
しっかりと引継ぎを行えるかどうかはあなたの腕の見せ所です。
業務についての理解が深ければ深いほど正確で迷惑を掛けない引継ぎが行えるでしょう。
自分の集大成だと思って取り組むのがいいかもしれません。
<最後の挨拶はしっかりと>
社内の人への挨拶は、退職願を提出してから最後の出社日までに済ませましょう。
最近では、退職のあいさつはメールで行うのが一般的になってきています。
ただし、
目上の人など相手によっては退職のあいさつメールを失礼に感じる人もいるので気をつけましょう。
自分と相手の関係性を考え、あいさつメールもしくは直接あいさつするかを使い分けましょう。
お世話になった方、目上の人には直接挨拶をする方がいいでしょう。
社内の人へは、退職を報告するというよりも
「最後のあいさつ」に近いものなので、勤務最終日に送るのが一般的です。
しかし、会社特有の慣例がある場合があるので、
これまでの先輩方などから受け取った、あいさつメールを参考にするといいでしょう。
メールを送るときの注意点として、必ず送り先をBCCで送付しましょう。
TOやCCでは他のメールアドレスが見えてしまうので気をつけましょう。
ここでも退職理由は、「一身上の都合」が基本です。
当然ですが、会社の愚痴や苦言は絶対に書かないようにしましょう。
<社外の人への挨拶も忘れずに>
社内へ送る退職メールと、社外へ送る退職メールは意味合いが違います。
社外には会社の信用を損ねない事、不安や不満を残さない事が鉄則です。
書き方3つのポイントについて解説します。
・退職日を明記する
退職日が一週間後なのか一ヶ月後なのかで、
先方の優先順位も変わってくるので、必ず明記しましょう。
・後任者や引き継ぎについて明記する
本来であれば後任者と一緒に直接あいさつに行くのがベストですが、
それができない場合はメールの中で名前を伝えておきましょう。
・私用の連絡先などは書かない事
あくまで会社を通しての関係なので一線を引いておきましょう。
また、転職先や退職理由などを書く事も、
会社やあなた自身の信用を損ねる事になるのでやめておきましょう。
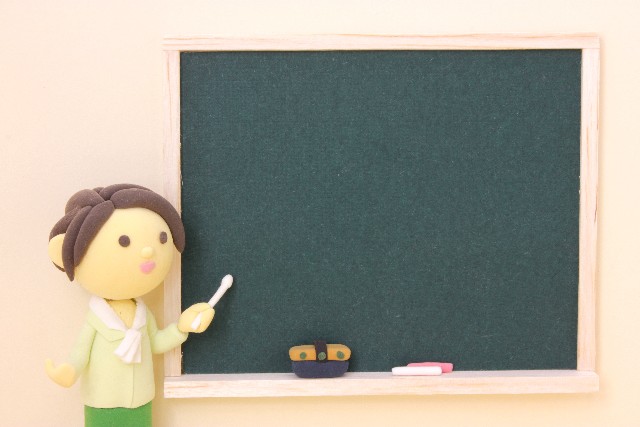
3.社内での動き方について
ここでは退職が決まった後、社内での動き方について説明していきます。
退職報告後から実際に退職の日までは相当なストレスを感じ、
中には嫌味を言ってくる人がいるかもしれません。
「辞めるのが決まってからが一番しんどかった」という方もいます。
そんな時の一番の解決方法は、社内の転職経験者に相談することです。
転職経験者は自身の経験から、親身に相談に乗ってくれることがほとんどです。
相談できる相手がいれば気持ち的にだいぶ楽になります。
今時、転職はさほど珍しいことではなく、意外と社内に何人か転職経験者はいるはずです。
転職のことを話したらみんな敵に見えてくるかもしれませんが、
実は応援してくれている人たちもいるのです。
そして円満退社をする為に、現職場に迷惑をかけることのないようベストを尽くしましょう。
退社が決まっていたとしても在職中は業務を最優先することが鉄則です。
給料をもらっている間はその企業の一員であり、企業への負担を最小限に抑えることを第一に、
マナーをわきまえた対応で最後まで社会人としての誠意をみせましょう。

4.転職に対する社会的イメージ
会社を辞めたいと考えているが、
転職に対する周りの目がネックで一歩踏み出せない人もいらっしゃるかもしれません。
たしかに一昔前までは、終身雇用制の意識が強く、
転職にネガティブなイメージを持つ人が多かったことは事実です。
しかし、現在では二人に一人が転職経験者と言われています。
実際に転職サイトDODAが、25〜39歳の正社員として就業する800人を対象に、
転職経験に関するアンケートを実施していたので紹介します。
| 年代 | 転職をしたことがある | 転職を検討したことがある | 転職、転職を検討したことがない |
| 全体 | 52.5% | 22.0% | 25.5% |
| 25〜29歳 | 35.3% | 33.1% | 31.6% |
| 30〜34歳 | 59.9% | 19.1% | 21.0% |
| 35〜39歳 | 53.5% | 20.2% | 26.3% |
このアンケート結果から、社会人の52.5%と半数以上の人が転職経験者であることがわかり、
このご時世、転職はさほど珍しいものではないことがわかります。
現在の仕事に多くのストレスを感じている場合は、
前向きに転職を考えるのがいいのではないでしょうか。
辞めたいのに続けるというのは精神衛生上よくありません。
最悪のケースでうつ病になってしまう場合でも会社は守ってはくれないでしょう。
「健全に生きていくための手法」の一つが仕事です。
それなのに仕事が理由で体調を崩してしまっては元も子もありません。
会社を辞めるということは決して「甘え」や「逃げ」ではありません。
退職するということに後ろめたさを感じる必要はありません。
仮にどんな退職理由であったとしても前向きな気持ちを持つことが大切です。
新しい環境で仕事ができる、新しいことを学べる、新しい人間関係がつくれる
会社を辞めることで新たな可能性が生まれるはずです。

5.入社して間もない場合
最後に、入社して間もない場合について少しご説明させていただきます。
新卒でも転職でも、入社したらまず『試用期間』という時期があります。
試用期間とは、企業が求職者を採用することになったときに、
長期雇用を前提としてその人の勤務態度、能力、スキルなどを見て、
本採用するかどうかを決定するために設けられている期間です。
(ただし、法的に設置が義務付けられているものではないため、通常と同じ雇用契約になります)
期間の長さについては、1~6ヶ月が一般的です。
入社して多くの方は、社風や業務が合わないからすぐ辞めるか、
辞めたいと思いつつ無理をして続けるかの2択になっている人が多いです。
入社して間もない時期に退職となれば、抱えるリスクも大きくなります。
衝動的に辞める前に、まず休みを取るということも1つの選択肢に入れてください。
入社して6か月経っていない場合は有給をとることができませんが、休みは必ずありますよね。
そのときに、「友達と会って話す」、「気分転換に運動をする」、
「旅行で気分をリフレッシュする」などをして心身を休めることも必要です。
そして、冷静になってからもう一度考え直してみてください。
まずは、初心に戻ってみて、なぜこの会社を選んだのかを思い出してください。
そして、辞めたい理由は改善することができないのかを考えてください。
また、会社の悪いところだけではなく、
良いところを探すともう一度頑張ってみようと気持ちに変わるかもしれません。
マイナスな考えばかりにならないようにしましょう。
入社してすぐ辞めるということは、経歴や転職の際に支障が出ます。
自分1人の考えで決めてしまわない方がいいです。
家族や信用できる人に相談し、客観的な意見を聞くことも1つです。
考え抜いた末、それでも辞めることを決意したら、
目次の1にかいてある流れで退職を進めていけば問題ありません。
(引き継ぎや、社内外への挨拶が必要でない場合は省略してください)
6.まとめ
退職の報告はなかなか言い出しにくいものです。
しかし前向きな理由で、
円満退社できるように動いていれば、社内の人たちも応援してくれるはずです。
ここで記載した円満退社のポイントを押さえて、無事に退社できるようがんばってください。




